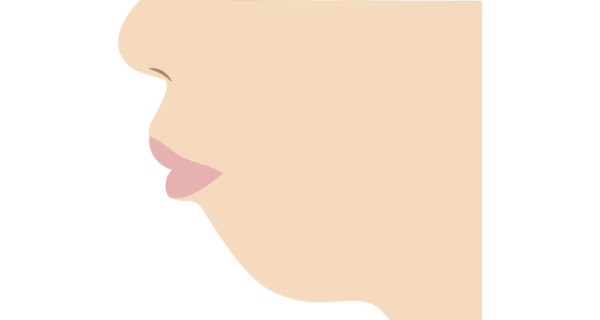Columns ―お役立ちコラム
「口ゴボだけど美人って人はいるの?口ゴボは治した方が良い?」 など、ふとしたきっかけで「もしかしたら自分が口ゴボかも?」と気づいてしまい、慌てている人も多いのではないでしょうか。 口ゴボは歯並びが綺麗に見えることが多く、美人とみられるケースもあります。 一方で、口ゴボによってコンプレックスを抱えてしまうケースも少なくありません。 本記事では、口ゴボに関する詳細をまとめています。 口ゴボが気になる人は、ぜひ記事内容をご確認ください。口ゴボとは?
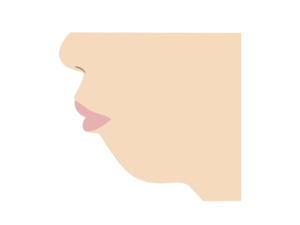
口ゴボ美人っているの?
口ゴボだけど美人に見られるケースは案外多いです。その要因は次の理由によるものです。 著作者:benzoix/出典:Freepik
著作者:benzoix/出典:Freepik
- 顎が大きいため歯並びがよく、笑顔が素敵な人が多い
- 口元がふっくらしているので若く見える
- 口ゴボを見慣れている人が多く、違和感よりも歯並びの良さの方が目立つ
結局口ゴボは治した方が良いの?
口ゴボの実態は主に上顎前突や上下顎前突です。噛み合わせの分類では「不正咬合」と呼ばれるもので、歯並びや噛み合わせの状態が悪いことを示しています。 不正咬合の場合、すぐに影響を及ぼすことは少ないです。将来的に口や体の健康へ影響を及ぼす可能性があるため、状態次第では歯列矯正をした方が良いケースもあります。 また、身体のダメージのみならず。見た目による精神的なダメージも十分に考慮しなければいけません。 出っ歯や口ゴボは程度によっては周りからからかわれたり、自分に自信が持てなくなるケースも多いです。 顔面のコンプレックスを持っていると、自然な笑顔が出にくくなります。笑顔が減ると印象が悪くなり、人付き合いが苦手になるかもしれません。 身体の状態とコンプレックスの観点から、口ゴボが気になる人は一度歯科医師へ相談してみましょう。口ゴボになる原因
口ゴボの原因となるものはいわゆる出っ歯です。歯の前突には「上顎前突」「下顎前突」「上下顎前突」があります。口ゴボになりやすいのは上顎前突と上下顎前突の2通りの不正咬合です。 不正咬合には逃れようのない先天的な要因と、おしゃぶり・指しゃぶり・舌癖・口呼吸等が原因となる後天的な要因があります。 先天的な要因は予防はできませんが、治療は可能です。後天的な要因は成長の過程で改善・修正できます。4つに分けられる口ゴボのタイプ
美人の評価ポイントはeラインと前歯の歯並びのよさです。eラインとは『エステティックライン』のことで、横顔の鼻のてっぺん、 顎の先を結んだ線のことを言います。 eラインより少し内側に上唇があるのが理想です。口ゴボはeラインより、口元が前にある状態のことを言います。 eラインを軸に4つの口ゴボのタイプを確認しましょう。下顎が引いているタイプの口ゴボ
下顎が引いているタイプの口ゴボはeラインから上下の唇がはみ出しています。口ゴボで歯並びが良い人の多くはこのタイプに該当します。 治療する場合、下顎に対して口元を後退させなければいけません。選択できる治療法は次の4つです。- 歯を抜かずに前歯を後ろに下げる
- 歯を抜いて前歯を後ろに下げる
- 下顎が後ろに位置している場合、手術で下顎を前に出す
- 歯列矯正で下顎を上前方へ動かす
上下の顎が前に出るタイプの口ゴボ
eラインを引いた時に、上下の顎が前に出てしまうタイプです。それに伴って口元が前に突出します。 治療にて歯か顎を後ろに下げなければいけません。 考えられる治療法は次の2つです。- インビザラインやワイヤーを使って上下の歯を後ろに下げる
- 外科手術にて顎を後ろに下げる
上の顎または唇が前に出ているタイプの口ゴボ
eラインから上唇が突出しており、出っ歯と呼ばれるタイプの口ゴボです。 基本的な治療法は次のとおりです。- 上の前歯を後退させつつ上唇も合わせて後退させる。インビザラインによる矯正も可能
- 上唇の骨そのものを後退させる。手術とワイヤー矯正が必要
目と額の周辺が引っ込んでいるタイプの口ゴボ
口元は正常な位置にあるのに、目や額の周辺が引っ込んでいるために、相対的に下顔面が上顔面にかけて前に出て見えるタイプです。 厳密には口ゴボではありませんが、全体で見ると口ゴボのように見えてしまいます。 治療を検討する場合、下顔面を後退させなければいけません。口元を後退させる矯正治療が選択されるケースが多いです。口ゴボの治療法とは?
口ゴボの治療は歯科医院か美容整形の2つが挙げられます。 歯科医院での口ゴボ治療は、各種歯列矯正にて対応します。美容整形の場合は、外科的治療による矯正手術が多いです。 矯正治療を主とする歯科医院での治療であっても状態によっては顎の骨を切って治療する外科矯正や骨格整形術が必要になるケースもあります。 美容整形外科での治療では、噛み合わせの問題に気をつけなければいけません。 噛み合わせが考慮されていないと咀嚼の問題が出たり、将来歯が抜けていく原因になることもあります。 治療の際は医師の説明を受けて十分に理解した上で進めましょう。 ここでは主に歯科医院で行われる口ゴボ治療について説明します。ワイヤー矯正
ワイヤー矯正はブラケット矯正とも呼ばれる治療法で、歯並びや噛み合わせの問題を修正するために行われる歯科矯正治療の一つです。ワイヤー矯正は、金属ブラケットとワイヤーを使用して歯を徐々に移動させ、正しい位置に整えることを目的としています。 上顎前突・上下顎前突の治療でも実績の多い治療です。マウスピース矯正
マウスピース矯正はクリアアライナー矯正とも呼ばれ、透明なプラスチック製のマウスピースを使用して歯を移動させる歯科矯正治療の一種です。代表的なブランドには、インビザライン(Invisalign)があります。 歯が動くように少しずつズレを作って作成し、ズレに向かって歯に力がかかることで歯を動かす仕組みです。 口ゴボの治療には対応する場合としない場合があります。小児矯正
小児矯正は、成長過程にある子供の歯並びや噛み合わせを改善するための歯科矯正治療です。通常、6歳から12歳くらいの乳歯と永久歯が混在する時期に行われることが多いです。 歯を動かす成人矯正と異なり、顎の成長を助けることで適切な咬み合わせを作っていきます。外科矯正
外科矯正は、顎の骨の異常を矯正するために行われる歯科手術と矯正治療の組み合わせです。特に、通常の矯正治療では解決できない重度の顎の不正咬合や顎変形症に対して行われます。 口ゴボの場合、咀嚼や発音に問題がある場合は、保険適用での治療が可能です。まとめ
口ゴボは矯正治療で改善できます。eラインが綺麗な横顔美人を目指したい人にとって、矯正治療はおすすめの方法です。 口元や横顔にコンプレックスを抱えている人は、一度歯科医院へ相談してみてはいかがでしょうか。 安岡デンタルオフィスの矯正治療は、歯並びの改善のみならず口腔内の機能回復を目的とした治療を行っています。 顎機能の矯正にも対応していますので、口ゴボが気になる方はぜひご相談ください。
出っ歯は押せば治るって本当なの?
出っ歯は素人が押して治せるほどシンプルなものではありません。 出っ歯を押して治せない理由を3つのポイントにて、説明します。- 出っ歯を押して自力で治すのは難しい
- 歯が動く仕組みとは
- 出っ歯を押すと危ない
出っ歯を押して自力で治すのは難しい
インターネットやSNSを見ていると、出っ歯を押していたら治ったという記載を見かけることがあります。 歯科医院へいかず、自分で治せるのであればそれにこした事はありません。良い治療法を見つけたと喜ぶ人も多いのではないでしょうか。 しかし、実際に自力で出っ歯を押し続けて綺麗に治すのはかなり難しいです。 歯に力をかけ続けて動かすことはできますが、素人の見立てで出っ歯を綺麗に収めるのは無理だと考えておいた方が良いでしょう。 歯医者になってから長らく矯正の勉強した人でも、思う通りに動かせないのが歯列矯正です。素人の手作業で成功する確率はかなり低いでしょう。歯が動く仕組みとは
矯正治療では、ワイヤーで引っ張って歯を動かしているわけではありません。 歯と歯を支える骨の間には歯根膜というクッションのような組織があります。矯正治療は歯根膜の吸収と骨の再生をうまく利用して、歯を動かします。 矯正治療は、綿密な計算と計画の上に成り立つ治療です。歯を押す行為には根本的な歯を動かす原理にかなっていません。 仮に歯を押して動いたとすると、他の要因が関連しているとしか考えられません。出っ歯を押すと危ない
歯に強い力を加えると、歯の根本が折れてしまう、動きに耐えられず歯の神経が死んでしまう、などのリスクが考えられます。 弱い力でも、継続的に力を与え続けると歯の根が骨に吸収されて短くなる「歯根吸収」が起きることも想定されます。 歯を押し続ける行為は、力加減や向きを考えずに行うため、歯根吸収は起きやすくなるでしょう。 歯根吸収を起こすと歯の根が短くなるため、耐性がなくなり抜けやすい歯になってしまいます。出っ歯を治す方法
出っ歯は不正咬合と呼ばれる症状の一つです。不正咬合は歯列矯正によって修正されます。 美容整形にて顎の骨を切る手術を受けて出っ歯を治す方法もありますが、骨格だけの問題に終始しない噛み合わせの不具合は、顎の骨を切っただけでは解決しないことも多いです。 根本的に出っ歯を治したい場合、歯列矯正を選ぶようにしましょう。 出っ歯を治すための矯正治療の方法を3つ、紹介します。- 全体矯正と部分矯正
- マウスピース矯正
- 表側矯正
- 裏側矯正
全体矯正と部分矯正
出っ歯を治すための矯正方法は全体矯正と部分矯正の2つです。 全体矯正は歯列全体の矯正治療で、部分矯正は一部の歯列を矯正する治療方法です。 基本的に全体矯正は部分矯正よりも矯正期間が長く、費用は割高です。 全体矯正は費用はかかるものの、歯列全体を矯正できるため、噛み合せまで細かく治療できるメリットがあります。 一方で部分矯正は矯正期間が短く、費用を抑えられますが、噛み合わせまでは対応できません。マウスピース矯正
マウスピース矯正は、微妙に形が違うマウスピースを順番に交換しながら装着して力をかけることで歯を動かす矯正方法です。 治療に使用するマウスピースは透明で、装着していることがわかりにくいということもあって、注目を集めている治療法です。 効果を得るには1日20時間の装着が必要ですが、食事や歯磨きの際は取り外しできます。 費用の目安は全体矯正で60〜100万円、部分矯正の場合、10〜40万円です。表側矯正
表側矯正は、ブラケットと呼ばれる金具とワイヤーを歯の表面に装着して、ワイヤーの力で歯を動かす矯正方法です。 古くからある矯正方法で、矯正と聞くと表側矯正をイメージする人も多いのではないでしょうか。 ブラケットのワイヤーは通常、金属製を使いますが、金属製はあまりに目立つため、白や透明の目立ちにくい素材を使うクリニックも多いです。 費用目安は、全体矯正の場合60〜130万円、部分矯正の場合30〜60万円です。裏側矯正
裏側矯正はブラケットとワイヤーを歯の裏側に装着してワイヤーの力で、歯を動かす矯正方法です。 歯の裏側に矯正装置をつけるため、表側矯正に比べると矯正していることがわかりにくいメリットがあります。 表側矯正よりも高い技術が必要になるため、対応していないクリニックもあります。 費用は表側矯正に比べてやや割高で、全体矯正の場合100〜170万円、部分矯正の場合40〜70万円です。出っ歯の状況をセルフチェック
出っ歯はセルフチェックでも確認できます。もしかしたら出っ歯かもしれない、と不安に思う方は、一度セルフチェックを試してみましょう。 著作権:Freepik
チェックポイントは次の3点です。
著作権:Freepik
チェックポイントは次の3点です。
- 上下の前歯の先端に隙間が4㎜程度ある
- 意識しないと唇が閉じられない
- 口を閉じると顎先にシワがよる
上下の前歯の先端に隙間が4㎜程度ある
上の前歯と下の前歯の先端の隙間を専門用語ではオーバージェットと言います。真横からみた場合に、オーバージェットが2㎜〜3㎜であれば正常です。オーバージェットが4㎜以上あると、出っ歯の部類です。 一般的に出っ歯の判定は、上の歯と下の歯のズレ幅で診断されます。意識しないと唇が閉じられない
出っ歯になると前に出ている歯が邪魔になるため、グッと力を入れないと唇が閉じられない症状が出ます。 気を抜くと口が開いた状態になるのが出っ歯です。 次の3つの症状に心当たりがある人は、出っ歯が疑われます。- いつも口が半開き
- 唇を閉じようとすると口周りが疲れる
- 口の中が乾燥しやすい
口を閉じると顎先にシワがよる
出っ歯の人は、口を閉じようとすると、出っ歯が邪魔をして上唇を下までおろすことができません。 その代わりに下唇を上に伸ばしてカバーしようとすると、無理に力が入ってしまい、顎にシワができてしまいます。 自分の口を閉じてみて顎先に妙なシワがよっている場合、出っ歯を疑った方が良いでしょう。出っ歯は放っておくとどうなる?
体の特徴として定着していれば問題はありませんが、中には出っ歯が身体へ影響を及ぼすケースもあります。 出っ歯が心身へ与える影響を2つのポイントにて、説明します。- 歯周病のリスクが増える
- 咬合力が低下
歯周病のリスクが増える
出っ歯と歯周病の関連性は広く認識されています。歯周病によって出っ歯になり、噛み合わせによってさらに歯周病が悪くなるという悪循環です。 このまま歯周病が進行すると、歯根膜や歯槽骨にも影響を与えることになり、最悪の場合、歯を失う可能性もあります。 出っ歯の違和感を感じる場合は、早めに歯科医院にてチェックしておいた方が良いでしょう。咬合力が低下
出っ歯によって咬合力が低下すると、咀嚼効率が悪くなり、さらには消化にまで影響する可能性があります。 その他、うまく発音しづらくなるなど、コミュニケーションにも支障が出てくるかもしれません。 口腔内の総合的な健康にも影響を及ぼす可能性も考慮しておきましょう。まとめ
出っ歯は見た目の問題だけでなく、咀嚼など体への影響まで懸念される症状です。見た目にも良いとは言い難いため、できれば早めに治療した方が良いでしょう。 ヨクシオファミリー歯科住道では、ワイヤー矯正やマウスピース矯正の他に、顎機能矯正にも対応しています。噛み合わせ全般についてお悩みの方はぜひご相談ください。 著作者:freepik
横顔にコンプレックスがありますか?写真や鏡に写った自分の横顔に不満を感じるなら、「口ゴボ」が原因かもしれません。正面から見ると歯並びは良いのに、なぜ?と思ったことはありませんか。本記事では、歯並びが良くても口ゴボで悩む方に向けて、原因や治療の必要性、放置するリスク、治療の選択肢や費用などについて解説していきます。
著作者:freepik
横顔にコンプレックスがありますか?写真や鏡に写った自分の横顔に不満を感じるなら、「口ゴボ」が原因かもしれません。正面から見ると歯並びは良いのに、なぜ?と思ったことはありませんか。本記事では、歯並びが良くても口ゴボで悩む方に向けて、原因や治療の必要性、放置するリスク、治療の選択肢や費用などについて解説していきます。
口ゴボとは?
口ゴボは、口元が前に出ている状態を指します。例えば、横から見たときに唇が前に突き出ている状態です。これは、上と下の前歯が前に出ているために起こります。鏡で横顔を見たときに、鼻先と顎先を結んだ線(エステティックライン)に対して唇が外側に出ていると、口ゴボの可能性がある、というわけです。治療して突出感が改善されると、横顔のラインが美しくなるでしょう。歯並びは良いのに口ゴボになる原因とは?
歯並びが良くても口ゴボになる原因は以下の通りです。骨格の遺伝
上顎骨や下顎骨の成長バランスが崩れると、口元が前に突出することがあります。上顎が前に出過ぎている、または下顎が後退していると、口ゴボの原因となります。顔の骨格や筋肉の特徴は遺伝の影響を受けるので、家族に口ゴボの人がいるとその傾向が現れやすいです。歯のはえている角度や位置
上の前歯が前方に傾いている、または下の前歯が後方に傾いていると、口元が前に出て見えます。歯列のアーチが前方に広がっている場合も、口ゴボの一因となります。口元の軟組織(皮膚や筋肉)の問題
唇の周りの組織に問題があるかもしれません。唇が厚かったり、口の周りの皮膚が厚いと、口が前に出て見えることがあります。子どもの頃の癖や習慣
幼少期に以下の癖や習慣があると口ゴボになります。- 口呼吸
- 柔らかいものばかり食べる
- 指しゃぶり
- 舌で前歯を押す
歯並びが良い口ゴボでも矯正治療はすべき?放置するリスクとは
口ゴボでも歯並びが良いなら、必ずしも治療する必要はありませんが、放置した場合のリスクもあります。口腔機能の問題
以下のような問題があるなら、治療をおすすめします。特に、口呼吸が増えると全身の免疫力が下がるので注意してください。- 発音しづらい
- 食べにくい
- 噛み合わせが悪い
- 口を閉じにくい
- 口呼吸になってしまう
顎関節症と消化器への影響
噛み合わせが悪くなると、顎関節に負担がかかり、顎関節症のリスクが高まります。また、食べ物をうまく噛み切れずに、胃腸や消化器に負担をかける恐れもあります。虫歯や歯周病リスクの上昇
口ゴボだと歯磨きがしにくいために磨き残しが増え、虫歯や歯周病になりやすくなります。また、磨き残しや食べ物のカスが溜まると、口臭の原因になります。見た目の問題
口元の出っ張りにより、顔のバランスが悪く見えます。自尊心や社会的な自信に影響を与えることもあるでしょう。改善することで笑顔や会話に自信が持て、人生の大きな転機になるかもしれません。口ゴボを自力で治す方法はある?
結論から言うと、口ゴボは自力で治すことは難しいです。多くの場合、遺伝による骨格の問題、子どもの頃の習慣や癖が原因となっています。まだ成長期の子どもであれば、口ゴボの原因となる癖を止めさせたり予防したりして、悪化を防ぐことはできるでしょう。しかし、大人の場合はすでに顎が発達し終えているので、自力で治すのは不可能です。口ゴボでも歯並びが良い場合の矯正方法
歯並びが良くても口ゴボで悩む方に向けた治療には、いくつかの選択肢があります。当院で提供している矯正治療は以下の通りです。 著作者:freepik
著作者:freepik
ワイヤー矯正(表側)
歯の表側にブラケットと呼ばれる小さな装置を取り付け、それをワイヤーで連結して歯を動かす矯正方法です。ワイヤーを調整することで歯並びを整えていきます。この方法はもっともスタンダードな歯列矯正で、多くの症例に対応可能です。舌側矯正(リンガル矯正)
舌側矯正(リンガル矯正)とは、歯の裏側(舌側)に矯正装置を取り付ける方法です。装置が見えにくいため、審美的な利点があります。外側からはほとんど見えないため、見た目を気にせずに矯正治療が行えます。インビザライン(マウスピース矯正)
マウスピース矯正は、透明な取り外し可能なマウスピースを使って歯を少しずつ動かし、歯並びを整える矯正方法です。マウスピースは患者様の歯型に合わせてカスタムメイドされ、数週間ごとに新しいマウスピースに交換して治療を進めます。目立ちにくく、取り外しができるため、食事や歯磨きがしやすいのが特徴です。セラミック矯正(ラミネートベニア)
歯の表面を少し削り、セラミックの素材を強力な接着剤で貼り付ける治療法です。軽度の口ゴボや歯の向きや並びに問題がある場合、セラミック矯正で対応できることがあります。根本的な治療ではありませんが、他の矯正に比べて費用が安く、治療期間も短いという利点があります。歯並びは良くても重度な口ゴボを治すなら美容整形や外科矯正
口ゴボで歯並びが良くても、あまりにも変形して顎の骨が出ている場合には外科的な手術(顎変形症手術)が必要になることがあります。顎変形症手術は、上顎と下顎の位置や大きさの異常によってバランスが合っていないため、噛み合わせがズレているのを治す手術です。 具体的には、上顎や下顎の骨の位置を調整し、正しい位置に移動させることで噛み合わせを改善し、顔のバランスを整えることを目的としています。口ゴボもこの手術で改善できますので、まずは矯正歯科医に相談してください。歯並びは良い口ゴボの矯正費用の目安
以下は安岡デンタルオフィスの費用の目安です。いずれも税込み価格、抜歯は別料金です。ただし、個人の状況により金額が変動することがあります。| ワイヤー矯正 | データ収集 ¥22,000 診断 ¥33,000 装置 上下表 ¥935,000 コンビネーション ¥1,155,000 リンガル ¥1,320,000 片顎 ¥495,000 調整料 ¥3,300/月 |
| マウスピース矯正(インビザライン) | データ収集・診断 ¥55,000 上下顎: ¥1,045,000 片顎:¥715,000 モデレートパッケージ (上下顎):¥550,000 モデレートパッケージ (片顎):¥440,000 |
| セラミック矯正(ラミネートべニア) | ¥110,000 |
口ゴボでも歯並びが良いと抜歯は不要?
軽度の口ゴボの場合、抜歯せずに治療できることがあります。成長期の子供や若者では、顎の成長を利用して歯列を広げたり、奥歯を後ろに移動させてスペースを作ったりします。また、歯と歯の間のエナメル質を少し削ってスペースを作ることもあるでしょう。しかし、重度の出っ歯や口ゴボ、目指すゴールによっては、抜歯が必要になることもあります。住道で歯並びが良い口ゴボを治すなら、ヨクシオファミリー歯科住道


歯茎にできる口内炎の種類とは?
歯茎にできる口内炎には、主に以下の4種類があります。それぞれの特徴、原因をわかりやすく説明します。アフタ性口内炎
一般的な口内炎で、口の中の粘膜に直径3〜5ミリの白っぽい潰瘍(アフタ)ができる状態です。この潰瘍は周りの粘膜とはっきり区別でき、刺激を受けると痛みます。悪化すると出血することもあります。 通常、1〜2週間で自然に治るため、痛みがそれほどひどくなければ特に治療しなくても問題ありません。何度も繰り返し発生するものは「再発性アフタ性口内炎」と呼ばれます。 よくある原因は以下です。- 免疫力の低下
- 栄養不足
- ストレス
- 寝不足
- 口内傷からの細菌・ウイルス感染
- 生理前や妊娠期
- ベーチェット病や潰瘍性大腸炎などの全身疾患
カタル性口内炎
口の中の粘膜が赤く炎症を起こし、ザラザラしたり白くなったりする口内炎です。アフタ性口内炎とは違って炎症の境界がはっきりしません。 口の中が焼けるように感じたり、口臭がしたり、酸っぱいものや辛いものを食べるとしみて痛みを感じます。 よくある原因は以下です。- 免疫力の低下
- 疲労
- 風邪などの体調不良
- 入れ歯や矯正器具など物理的な刺激や傷
- 虫歯、歯周病、歯槽膿漏などの口内疾患
- 過度な喫煙
- ビタミン不足
- 胃腸の調子が悪い
カンジダ性口内炎
もともと口の中にいる常在菌、カンジダというカビの一種が口の中で増殖して起こる口内炎です。頬の内側や唇の裏側などに、白い薄皮(偽膜)ができ、簡単に剥がれます。剥がすとその下の粘膜が赤くなっていて、周りの粘膜も赤く腫れていることがあります。放置すると口全体に広がることも。 症状は口の中の違和感や舌のしびれ、味覚の異常を感じ、大人だけでなく乳幼児にも発症します。 よくある原因は以下です。- 常在菌であるカンジダ菌(カビ)の過剰増殖
- 糖尿病、血液の病気、がんなど他の疾患を患っている
- 乳幼児、高齢者、妊婦など体力や抵抗力が弱い
- ステロイド剤や抗生物質の長期間服用
ヘルペス性口内炎
単純ヘルペスウイルス(HSV)の感染によって起こるウイルス性口内炎の一種です。乳幼児に多く見られ、口の粘膜に水ぶくれができたり、歯ぐきが炎症を起こしたり、発熱することがあります。水ぶくれが破れると潰瘍になり、激しい痛みを伴い、食事や水分を取れず脱水症状になることも。 一度感染するとウイルスが体内に残るため、大人になっても抵抗力が低下した場合などに再び発症しやすくなります。 よくある原因は以下です。- 免疫力の低下
- 口内の傷や炎症による物理的な刺激
- 過度な紫外線
- 月経周期や妊娠によるホルモンの変動
- がん治療やエイズなどで免疫力が著しく低下
- ヘルペスウイルスは人から人、モノから人へと感染
その他の口内炎
- 喫煙者によく見られる「ニコチン性口内炎」
- 特定の食べ物や薬、金属などへのアレルギー反応で起こる「アレルギー性口内炎」
- 全身に炎症を起こす病気、口内炎もその症状の一つである「ベーチェット病」
歯茎にできる口内炎に似た間違えやすい病気
以下の病気は自然治癒しませんので、気になる症状があれば、できるだけ早く診察を受けてください。歯肉がん
歯肉がんは、歯茎にできる悪性腫瘍(がん)です。歯茎の細胞が異常に増殖してできるもので、他の組織や臓器に広がることがあります。 初期は歯茎の腫れ程度ですが、進行すると表面がカリフラワーのような凸凹した形状になり、出血や痛みを伴うことがあります。舌がん
舌の側面や舌の裏側、舌の先端などにがんが発生します。口腔がんの半数以上を占めるがんです。患部の色がアフタ性口内炎と似ています。 初期段階では、舌に小さな白い斑点や潰瘍ができることがありますが、痛みがないため見過ごされやすいので注意してください。 進行すると、痛みや出血、舌の動きの制限などの症状が現れます。舌がんは早期に見つかれば治療が可能ですが、進行すると治療が難しくなります。白板症(はくばんしょう)
口の中の粘膜が何度も摩擦を受けると、白色の板状(斑状)に変化する病気ですが、痛みはありません。 見た目はカンジダ性口内炎に似ていますが、特に舌の縁にあらわれた場合は舌がんに移行するリスクが高いといわれています。がんになる前段階と考えられているので注意してください。口内炎で歯茎が白くなる原因は何ですか?
痛くないけれど治らない白いできものがあったら、「フィステル」の可能性があります。別名は瘻孔(ろうこう)や内歯瘻(ないしろう)、サイナストラクトとも呼ばれています。 歯の根管には神経や血管が通っており、この部分が感染すると痛みや膿が発生します。体は溜まった膿を排出しようと、歯茎や口の内側に向かって“膿の排出口”(フィステル)を作ります。 フィステル自体は痛くないことが多いですが、膿が溜まっている部分は痛みや腫れを伴うこともあります。また、 自然治癒しないので、放置すると感染が広がって抜歯する可能性も出てくるので、早めに治療しましょう。 フィステルについて詳しく知りたい方は、以下のコラムを参考にしてください。 歯茎のできものの正体とは?フィステルの原因についても紹介歯茎の口内炎は市販薬で対処できる?
口内炎を治す市販薬には、いくつか種類があります。軽度の場合であれば市販薬でも対処が可能です。- パッチタイプ
- 軟膏タイプ
- スプレータイプ
- 洗口液タイプ
- ドリンクタイプ
- 内服薬
歯茎にできた口内炎を早く治すには?
口腔内の清潔を保つ
食後は必ず歯を磨き、口腔内を清潔に保ちます。さらに食後や寝る前にうがい薬(イソジンなど)を使ってうがいをし、口内の細菌を減少させることも大切です。市販薬を使用
痛みをやわらげ、治癒を促進します。軟膏、パッチ、スプレーなど、自分に合ったものを選びましょう。ビタミンの摂取
ビタミンB群を多く含む食品を摂取することで、口内炎の治りを早めることができます。サプリメントを利用するのも一つの方法です。刺激物を避ける
酸味や辛味の強い食べ物、アルコール、タバコなどを避けることで痛みを軽減し、治癒を促進します。生活習慣の改善
ストレスや睡眠不足は口内炎の原因になるため、リラックスできる時間をつくり、十分な睡眠を心がけましょう。また、口呼吸を避け、水分補給をしっかりしてください。歯科医院を受診する
症状が1〜2週間で治らない時や、頻繁に口内炎ができる場合は、診察を受けることをおすすめします。短期間で治したいなら、歯医者さんでレーザー治療も検討してください。歯茎の口内炎が治らないときは受診しましょう

口腔内の歯科金属アレルギーの症状とは?
 口腔内の金属アレルギーの症状は、以下の通りです。
口腔内の金属アレルギーの症状は、以下の通りです。
- 掌蹠膿疱症(しょうせきのうほうしょう)
- アトピー性皮膚炎
- 全身の不快感
- 口内のかゆみや痛み
- 口内炎
- 口唇炎
- 舌炎
- 歯茎の炎症
- 味覚異常
口腔内で金属アレルギーが起こるメカニズムとは?
口の中で金属アレルギーが起こる主な原因は、銀歯の詰め物や被せ物などの金属によるものです。 金属アレルギーが起こる理由は、口の中の唾液によって金属が溶けるためです。金属は水分がある環境で溶け出す性質があります。唾液には水分が含まれているため、銀歯などの歯科用金属は長期間にわたって唾液にさらされることになります。そのため、口の中で金属が少しずつ溶け出し、体内に取り込まれてしまうというわけです。 金属が体内に蓄積され、一定量を超えると、人によってはさまざまな場所でアレルギー症状が起こることがあります。歯科治療でアレルギーの原因になる金属とは?
歯科治療で使用される金属には、金、銀、銅、白金(プラチナ)、亜鉛、水銀、ニッケル、コバルト、スズ、パラジウム、クロム、チタンなどがあり、2種類以上の金属を混ぜたものが「合金」です。 歯科治療でアレルギーの原因となる主な金属は、以下の通りです。金銀パラジウム合金
保険でつくられた銀歯は、詰め物や被せ物、入れ歯のバネにも使われます。銀だけでなく、金、銅、その他さまざまな金属が含まれています。金属アレルギー検査で約半数の人に陽性反応が出る金属といわれ、使用禁止する国もあります。銀合金
差し歯の土台(メタルコア)、詰め物、被せ物に使われます。主に銀、銅、亜鉛が混合され、一部には微量のニッケルが含まれています。コバルトクロム合金
入れ歯の土台やバネに使用されます。コバルトとクロムが主成分で、一部にはニッケルが含まれています。アマルガム
現在はほとんど使用されませんが、詰め物に水銀が含まれていました。水銀を50%含み、少量のスズや銅、亜鉛などが混合されており、健康リスクの面から使用禁止する国もあります。 中高年の患者様の中には、かつて治療を受けた部位に、この材料が含まれている可能性もあるので注意してください。歯科金属アレルギーになった場合の対処法とは?
口腔金属アレルギーが確認されたら、口腔内にある金属素材をすべて取り除きます。その後は金属を使用しないメタルフリー治療や代替材料を検討してください。たとえば、セラミックやジルコニア、プラスチック(コンポジットレジン)といったメタルフリーの素材が最適です。 ただし、金属アレルギーを引き起こす金属を取り除いても、すぐに症状が治まるわけではありません。完全に治るまでには数ヶ月かかるので、定期的に歯科医院を受診する必要があります。メタルフリー治療のメリットは?金属とセラミックの違いを比較
メタルフリー治療とは金属製品を使用せず、金属フリーの材料を用いて行われる歯科治療のことです。金属フリーの材料には、セラミックやプラスチック(コンポジットレジン)などが含まれます。 当院としては天然歯に近く、審美的や機能的にも優れているセラミックをおすすめしています。アレルギー反応のリスクを軽減し、身体に馴染みやすいので安心です。 金属製とセラミック製の歯の違いは、以下の通りです。| 特性 | 金属製 | セラミック製 |
| 審美性 | 目立ちやすい | 自然な見た目で美しい |
| 耐久性 | 強いが経年劣化しやすい | 強くて経年劣化が少ない |
| 金属 アレルギー反応 | 引き起こす可能性あり | リスクは低い |
| 保険 | 保険適用 | 自費診療 |
| 清掃性 | 歯垢がつきやすい | 表面が滑らかで清掃しやすい |
| むし歯のリスク | 金属部分の周りに むし歯ができやすい | 天然歯と同様のリスク |
歯科金属アレルギーの可能性がある場合、最初に何をすべき?
口腔金属アレルギーの症状や異変に気づいたら、以下のステップを踏むことが大切です。①歯科医に相談する
症状や不快感があれば、まずは歯科医に相談します。歯科医は口腔金属アレルギーの可能性を評価し、適切な診断や治療法を提案します。②アレルギー検査を受ける
歯科医の指示に従い、提携する皮膚科医院(大学病院も含む)での「パッチテスト」を受けてください。パッチテストが難しい場合は、血液検査で代用することもあります。③金属の除去
パッチテストで陽性反応があれば、金属を取り除きます。(同意が得られた場合のみ)④仮歯で経過観察
口腔金属アレルギーの症状や影響を定期的に経過観察します。症状が現れたら、早めに歯科医に連絡してください。⑤メタルフリー治療や代替材料の検討
口腔金属アレルギーが確認されたら、金属を使用しないメタルフリー治療や代替材料を検討します。金属フリーの治療法は、アレルギー反応を軽減するための有効な方法の一つです。まとめ
歯科治療における金属アレルギーの症状は、口内よりもむしろ口以外の部分に症状が出ることが多く、一見すると歯とは関係なさそうな場所で現れやすいため、気づきにくいことがあります。 皮膚科で治療しても改善しない湿疹などの症状があれば、歯科金属アレルギーを疑ってみてください。まずは歯科医に相談し、皮膚科や大学病院でアレルギー検査を受けることを検討しましょう。 もし検査結果が陽性であれば、口内に使用されている銀歯や銀の詰め物、被せ物などの金属を取り除き、代わりにセラミックやプラスチック(コンポジットレジン)などの金属フリー素材に交換することで症状が改善される可能性があります。 金属アレルギーに関するお悩みやセラミック治療について詳細を知りたい方は、ヨクシオファミリー歯科住道にいつでもご相談ください。また、金属を非金属に置き換える治療に興味がある方には、以下のコラムも参考にしてみてください。 内部リンク:昔の銀歯はセラミックへ交換すべき?セラミックの詰め物や被せ物のメリットを紹介ホワイトニングの種類
ホワイトニングとは、歯を削らずに漂白剤(主に過酸化水素)で化学的に白くするブリーチ(漂白)のことを指します。私たちの歯はコーヒーや紅茶、カレー、チョコレートなどの飲食物やタバコの影響で、着色汚れ(ステイン)となって歯が黄ばみます。ホワイトニングの目的は、これらの色素を取り除いたり、歯に付着した色素を薄めたりすることです。
オフィスホワイトニング
歯科医院で行われる方法です。歯の表面に過酸化水素のジェルを塗り、専用機器で光を当てて歯をより白くします。1時間程度で、歯が白くなるのが特徴です。ホームホワイトニング
自宅で行う方法です。マウスピースに過酸化尿素を塗布して装着します。時間はかかりますが、好きなときに自宅でできる利点があります。デュアルホワイトニング
オフィスホワイトニングとホームホワイトニングを併用した方法です。短期間でできるだけ早く効果を出したい方に適しています。ホワイトニングの仕組みとは?
ホワイトニングは、ホワイトニング剤を歯の表面に塗ることで始まります。この成分が歯に浸透し、歯の色素を分解して化学反応を引き起こし、歯を白くする仕組みです。 ホワイトニング剤には、「過酸化水素」や「過酸化尿素」といった成分が含まれています。これらは漂白剤や殺菌剤としても使用される成分です。 歯科医が使用するホワイトニング剤は、口の中で安全に使用できる濃度に調整されています。この薬剤が歯に浸透すると、色素が分解または薄められ、歯が白くなります。 歯を白くする方法には、以下の2つがあります。歯の表面に付着した色素を取り除く方法(漂白)
ホワイトニング剤で歯の表面に付着した色素や汚れを分解します。これにより、歯の表面がより白く明るく見えます。ただし、元々の歯の色以上の白さを得ることはできません。歯の表面構造を変化させて明るくする方法
ホワイトニング剤を歯の表面に浸透させ、歯の結晶構造を変化させます。これにより、歯の表面が滑らかになり、光の反射が増えて歯がより明るく見えます。この方法は歯科医院で行うオフィスホワイトニングで使われ、本来の歯の色以上の白さを目指せますが、しみることがあるかもしれません。オフィスホワイトニングとホームホワイトニングの違いとは?
オフィスホワイトニングとホームホワイトニングの違いを、以下の表にまとめました。| 項目 | オフィスホワイトニング | ホームホワイトニング |
| 場所 | 歯科医院 | 自宅 |
| 希望の色 | 透明感やツヤ感を求める | 真っ白さを求める |
| 回数 | 1回1時間程度 約3~6回の通院 | 1日2時間を2週間 数週間から数ヶ月にわたって行う |
| 方法 | 歯科医師が専用機器を使用 | 歯科医師から提供されたキットを使い、 自分で行う |
| ホワイトニング剤濃度 | 30%〜35%(過酸化水素) | 3%~10%(過酸化尿素) |
| 効果 | 1回の訪問で効果あり | 効果は徐々に現れる |
| 持続性 | 3〜6か月程度 | 6か月~1年程度 |
| 費用相場 | 1万〜7万円程度(1回) | 1万5000円~4万円程度 |
歯医者で行うホワイトニングの光照射の仕組みとは?
歯医者で行うホワイトニングでは、過酸化水素が30%〜35%含まれており、歯の表面構造を変化させて歯を白くします。効果的に白さを出すための重要なポイントは「光照射」です。 光照射が重要な理由は、光のエネルギーが過酸化水素の反応を促進するからです。光が当たると、過酸化水素がより活性化し、歯の表面の色素を分解する力が強まります。つまり、光を当てることで、ホワイトニングの効果が高まるのです。 そのため、歯科医院ではホワイトニング薬剤を塗布した後に特殊な光を当てます。そうすることで、ジェルの漂白成分がより効果的に働き、歯の表面に付着した色素を酸化・分解して、歯がより白くなるわけです。ホワイトニングのデメリットとは?
歯ぎしりが激しい方や知覚過敏の方は、ホワイトニングの薬剤で歯がしみる可能性があります。歯ぎしりをすると歯にひびが入り、薬剤が浸透しやすくなるためです。 さらに、オフィスホワイトニングでは痛みを感じなくても、ホームホワイトニングではしみることも(その逆もあります)。これらの症状は一時的なもので、使用をやめれば1日〜2日以内に治まります。1週間以上続く場合は歯科医に相談してください。効果的なホワイトニングのための汚れ別対処法
ホワイトニングで効果を出すには、汚れの種類によって対処法が異なることを知っておいてください。歯が着色する原因には「外因性の着色」と「内因性の着色」の2種類があります。外因性の着色
歯の表面についた色素によって歯が黄ばんで見えることです。コーヒーや紅茶、カレーやチョコレートなどの飲食物、タバコのヤニなどによって起こります。 改善方法は、プロによるクリーニング(歯面研磨)だけで本来の色を取り戻せます。さらに歯を白くしたいという場合は、歯科医が提供するホームホワイトニングキットや、オフィスホワイトニングなどのプロフェッショナルなホワイトニングもあり、高濃度の過酸化水素などの薬剤を使用して歯の表面の色素を取り除きます。内因性の着色
内因性の着色は、歯そのものが変色することによって起こります。原因としては、加齢による歯の色の変化や抗生物質などの薬物使用、虫歯の治療で歯の神経を抜いた場合や歯の打撲などによるものです。外因性の着色と比較すると、効果を実感するまでに時間がかかります。 改善方法は、より強力なホワイトニング剤や歯科医による特殊な治療が必要で、完全に取り除くのは難しいこともあります。別の方法として、歯の表面を少し削り、薄いセラミックを貼り付けるラミネートベニアによる改善も検討してみてください。ヨクシオファミリー歯科住道のホワイトニングは1回の通院で効果を実感

ホワイトニング